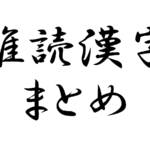熟語といえば二字であり、長いものだと四字熟語というものもあります。四字熟語は専用の辞典も多く出版され、漢検でも独立した設問として出題されるテーマである一方、「三字熟語」は余り取り上げられている印象がありません。
今回はそんな三字熟語を集めてみようと思います。
三字熟語の一覧(※更新中)
原則は漢検漢字辞典に掲載されているものとし、未掲載の熟語については備考に掲載。
動植物の名称(松藻虫(まつもむし)、法螺貝(ほらがい)など)、熟字訓(混凝土(コンクリート)など)、人名・地名や施設名等の固有名詞(愛迪生(エジソン)、渟足柵(ぬたりのき)、紫宸殿(ししんでん)、聚楽第(じゅらくだい)、輪島塗(わじまぬり)など)は原則として除外。
また、三字熟語というと紫外線、修羅場、大黒柱のように一般化したワードも含まれますが、こういった言葉を加えると膨大になることから独断で除外しているケースがありますので、ご了承ください。
| 読み方 | 漢字 | 意味 | 備考 |
|---|---|---|---|
| あかだな | 閼伽棚 | 仏に供える水や花などを置く棚。 | |
| あくたろう | 悪太郎 | いたずらな子供や乱暴狼藉をはたらく男をののしって言う語。 | |
| あくびょうどう | 悪平等 | それぞれの個性や特質を無視して一律に同じ扱いをするため、却って不公平であること。形式だけの平等で、本当は不平等になっていること。 | |
| あそうぎ | 阿僧祇 | ①数えきれないほどの大きな数。②数の単位。10の56乗、また10の64乗。 | |
| あとぶつ | 阿堵物 | 銭の異称。 | |
| あへんくつ | 阿片窟 | 阿片を吸引させる秘密の場所。 | |
| あみだ | 阿弥陀 | ①西方仏教にいて、人々を極楽へ導くとされる慈悲深い仏。阿弥陀仏。②阿弥陀籤(あみだくじ)の略。何本かの縦線に横線を加えて引く籤。 | |
| あめざいく | 飴細工 | ①あめで動物などの形を作ったもの。②見かけは立派だが、内容の伴わないもののたとえ。 | |
| アラカン | 阿羅漢 | 全ての煩悩を絶ち、悟りの境地に達した人。小乗仏教では最高の地位とされる。 | |
| あらみたま | 荒御魂 | あらあらしい神霊。 | |
| あらむしゃ | 荒武者 | ①勇ましくあらあらしい武士。②乱暴なほど意気盛んな者。 | |
| あらりょうじ | 荒療治 | ①患者の苦痛を無視し、手荒な治療を行うこと。②思い切った改革をすること。物事を手荒に捌くこと。 | |
| あんあんり | 暗暗裏/暗暗裡 | 誰にも気づかれずに。こっそり。「ーに事を運ぶ」 | |
| あんけんさつ | 暗剣殺 | 九星の方角の一つ。子や召使に殺されるおそれがある最凶の方位。 | |
| あんそくにち | 安息日 | 仕事をしないで宗教上の儀式を行う日。 | |
| あんぽんたん | 安本丹 | あほう。ばか。愚か者。人をののしって言う語。 | |
| いかいよう | 胃潰瘍 | 胃の粘膜が傷つき、ただれたりくずれたりする病気。 | |
| いくじ | 意気地 | 自分の考えを貫こうとする気力。 | |
| いけいれん | 胃痙攣 | 胃やその付近が急に激しく痛む症状。しゃく。 | |
| いこじ | 依怙地/意固地 | あくまでも自分の主張を貫こうとする、頑なな態度。片意地。 | |
| いしゃりょう | 慰藉料/慰謝料 | 生命・身体・自由・名誉・財産などが侵害された時、その精神的損害を償うために支払われる金銭。 | |
| いじょうだか | 威丈高 | 相手を威圧するような態度をとるさま。「ーに話す」 | |
| いしょうびつ | 衣装櫃 | 衣服を入れてしまっておくための、ふたのついた大形の箱。 | |
| いじょうふ | 偉丈夫 | 体格が立派で頼もしそうな男。 | |
| いそうがい | 意想外 | 思いもよらないこと。 | |
| いだてん | 韋駄天/韋陀天 | ①仏法や寺院の守護神。足が非常に速いといわれる。②足が非常に速い人のたとえ。 | |
| いちげんきん | 一弦琴/一絃琴 | 琴の一種。約1.1mの胴に一本の弦を張った琴。中国からの伝来。 | |
| いちけんしき | 一見識 | しっかりした、ひとかどの意見や考え方。 | |
| いちこつちょう | 壱越調 | 雅楽の六調子の一つ。十二律の一番目、壱越を主とする調子。 | |
| いちせいめん | 一生面 | 新しく切り開いた芳香。新しく工夫や方法を編み出した方面。新機軸。 | |
| いちめがさ | 市女笠 | 竹や菅で編んで中央部を高くした笠。 | |
| いっかごん | 一家言 | ①その人だけの独特な主張や意見。②ひとかどの見識を備えた意見。 | |
| いっこくもの | 一刻者/一国者 | 頑固で自説を曲げない人。一本気で融通の利かない人。 | |
| いっすいかん | 溢水管 | 堤防を越えてあふれ出た水を流す管。 | |
| いっせつな | 一刹那 | 非常に短い時間。 | |
| いっていじ | 一丁字 | 一個の文字。一字。 | |
| いっぽんやり | 一本槍 | ①槍一本で敵に勝つこと。②一つの考えや手法で押し通すこと。 | |
| いとわっぷ | 糸割符 | 江戸時代、外国船がもたらした生糸売買の独占権を堺・京都・長崎など特定の商人に与えた制度。また、この権利を示す証札。 | |
| いにょうち | 囲繞地 | ①袋地(他人の所有地に囲まれ、私道だけで行動に通じる土地)を囲んでいる土地。②他の一国に完全に囲まれている領土。 | |
| いぶんし | 異分子 | 仲間と思想や行動などが違っていて集団になじまない者。 | |
| いまちづき | 居待月 | 陰暦の18日の月。8月18日の月。 | |
| いもづるしき | 芋蔓式 | 芋の蔓を引っ張ると芋がずるずると連なって出てくるように、次々と続いて関連するものが現れ出ること。 | |
| いれいさい | 慰霊祭 | 死んだ人の魂を慰めるための祭り。 | |
| いろは | 伊呂波 | ①いろは歌の最初の3字で、いろは歌47字の総称。②物事の初歩。 | |
| うじすじょう | 氏素性/氏素姓 | 家柄や家筋。生まれや家系・経歴。「―の知れない人」 | |
| うしょくしょう | 齲蝕症 | むしばの別称。 | |
| うばい | 優婆夷 | 在家のまま仏門に入った女性。信女。近事女(こんじにょ)。 | |
| うばそく | 優婆塞 | 在家のまま仏門に入った男性。信士。近事男(こんじなん)。 | |
| うぶすながみ | 産土神 | 生まれた土地の守護神。鎮守の神。 | |
| うらぼん | 盂蘭盆 | 7月または8月の13日から15日にかけて、先祖の霊を迎え供養する行事。 | |
| うりざねがお | 瓜実顔 | 瓜の実のように、色が白くて面長な顔。 | |
| うんげやき | 雲華焼 | 焼く時の操作で器の表面に、雲がかかったようなぼやけた黒斑のむらを出す焼き方。また、その手法で焼いた陶器。 | |
| うんげんにしき | 暈繝錦/繧繝錦 | 暈繝彩色の手法を取り入れた織物。 | |
| うんげんべり | 暈繝縁/繧繝縁 | 繧繝錦で作った畳のへり。 | |
| うんこんどん | 運根鈍 | 成功するには、運が強いこと、根気があること、粘り強いことの3つが必要であるという教え。 | |
| うんじょうびと | 雲上人 | ①宮中の人。貴族。皇族。②昔、宮中清涼殿の殿上の間にのぼることを許された四位、五位の人、及び六位の蔵人。 | |
| うんどんこん | 運鈍根 | 「運根鈍」に同じ。 | |
| うんりゅうがた | 雲竜型 | 相撲で、横綱の土俵入りの型の一つ。せりあがるとき、左手を曲げ右手を横に延ばす。 | |
| えいきごう | 嬰記号 | 音楽で、元の音を半音高くすることを示す記号。シャープ(♯)。 | |
| えいこうだん | 曳光弾 | 弾道や着弾点が良くわかるように、明るい光を発しながら飛ぶ弾丸。 | |
| えもんだけ | 衣紋竹 | 竹でできた衣服を吊るすための道具。 | |
| えんかんぎょ | 塩干魚/塩乾魚 | 塩漬けにして乾燥させた魚。 | |
| えんぷくか | 艶福家 | 多くの女性からもてはやされる男性。 | |
| えんぶだい | 閻浮提 | ①須弥山の南方海上にあるという大陸の名。諸仏が出現するとされた。②この世。現世。もとはインドを指したが、後に人の住む世界を指す。 | |
| えんまちょう | 閻魔帳 | ①死者の生前の善悪が書いてあり、閻魔大王がそれを見て審判を下すという帳面。②教師が受け持ちの生徒の成績・品行などを記しておく帳面。③警察官が持っている手帳。 | |
| えんままいり | 閻魔参 | 陰暦の1月と7月の16日に閻魔堂へ参拝することこの日は地獄の釜開きで、亡者も責め苦を免れるという。使用人のいる家では藪入りと称して休暇を与えた。 | |
| おあいそ | 御愛想 | ①お世辞。②もてなし。③勘定書き。 | |
| おいど | 御居処 | お尻。 | |
| おうもうにち | 往亡日 | 凶日の一つ。陰陽道で外出・旅行・出陣などを忌み嫌う日。1年に12日ある。 | |
| おえしき | 御会式 | 日蓮宗で、日蓮上人の命日の10月13日に行う法会。 | |
| おくつき | 奥津城 | 墓。墓所。 | |
| おしたじ | 御下地 | 醤油。 | |
| おしゃか | 御釈迦 | だめになること。また、だめになったもの。できそこない。 | |
| おたふく | 阿多福 | ①おかめ。②顔立ちの悪い女性。女性をののしって言う葉。 | |
| おてしょ | 御手塩 | 浅く小さい更。手塩皿。主に女性語。 | |
| おてんば | 於転婆/御転婆 | 若い娘がしとやかさにかけ、活発に行動すること。また、その娘。 | |
| おとごづき | 乙子月 | 陰暦12月の異称。末子を乙子ということから。 | |
| おとさた | 音沙汰 | 頼り。連絡。 | |
| おんようけ | 陰陽家 | 陰陽道を司る家柄。また、その人。 | |
| おんようじ | 陰陽師 | 律令制で、宮中の陰陽寮に属して、陰陽道によって天文・地相・占いなどを司った職。中世以降、民間で加持祈祷をするものを指す。 | |
| おんようどう | 陰陽道 | 古代中国から伝わった陰陽五行説に基づく学問。天文や暦、占いなどを研究し、吉凶を占う。 | |
| かいきえん | 怪気炎/怪気焔 | 調子が良すぎて信じがたい盛んな意気。 | |
| かいしょう | 甲斐性 | 気力や才覚にあふれ、頼りになる性質。特に、経済力についていう。 | |
| かいらいし | 傀儡師 | ①人形使い。②他人を陰で操る者。 | |
| かおみせ | 顔見世 | ①人々に初めて顔を見せること。②顔見世興行の略。 | |
| かげひなた | 陰日向 | ①日の当たる所と当たらない所。②人前に出ると言葉や態度が変わること。 | |
| かげべんけい | 陰弁慶 | 身内には強がって見せるが、他人の前では意気地がないこと。 | |
| かさいるい | 果菜類 | 果実部分を食用とする野菜類。茄子、トマト、カボチャなど。 | |
| かしゃがた | 花車方 | 歌舞伎の役柄の一つ。女形のうち年増・老女などの歳のいった役。 | |
| かしょうざ | 迦葉座 | 仏像を安置するハスの葉の形をした台座。 | |
| かしょうぶつ | 迦葉仏 | 過去七仏の第六番目の仏。釈迦の直前に出現した。 | |
| がたろ | 河太郎 | 河童の別称。西日本でいう | |
| かつかんぱく | 褐寛博 | ①粗末なダブダブの衣服。②身分の低い卑しい人。無頼漢。 | |
| かなくぎりゅう | 金釘流 | 下手な字をあざけっていう言葉。 | |
| かびや | 鹿火屋 | 夜、シカなどの獣が荒らさないように、火を燃やして見張りをする番小屋。 | |
| かほんか | 禾本科 | イネ科の旧称。 | |
| かみすきぶね | 紙漉槽 | 紙をすくときに、原料を溶かした水を入れておく水槽。 | |
| からねんぶつ | 空念仏 | ①心が伴わず口先だけで唱える念仏。②実行が伴わず口先だけの主張。 | |
| かりゅうかい | 花柳界 | 芸者や遊女の社会。いろまち。遊里。 | |
| かりんとう | 花林糖 | 菓子の一種。 | |
| かんこうれい | 箝口令/鉗口令/緘口令 | ある事柄について発言を禁止すること。また、その命令。 | |
| かんごり | 寒垢離 | 心身を清めるため、寒中に冷水を浴びて神仏に祈ること。寒行。 | |
| かんざらい | 寒復習 | 寒中の早朝などに芸事の復習や練習をすること。 | |
| かんじつげつ | 閑日月 | ①用事や仕事のない暇な時期。②あくせくせず、心に余裕のあること。 | |
| かんすぼん | 巻子本 | 印刷した紙や書き写した紙などを横長に接いで、軸に巻いた書物。 | |
| かんたんし | 邯鄲師 | 客が眠っている間にその金品を盗む者。枕探し。 | |
| かんもじ | 閑文字 | 無駄な字句や文章。無益な言葉。 | |
| ききょらい | 帰去来 | 官職をやめて故郷へ戻るために、その地を去ること。 | |
| きこうぼん | 稀覯本 | 数が少なく珍しい本。めったに見られない本。 | |
| きこにち | 帰忌日 | 陰陽道で、縁起の悪い神が支配するとして遠出・帰宅・結婚などを嫌った日。 | |
| きさらぎ | 衣更着 | 陰暦2月の異称。 | |
| きっきゅうじょ | 鞠躬如 | 体をかがめて慎みかしこまるさま。 | |
| きっそう | 吉左右 | ①よい便り。喜ばしい報せ。②良いか悪いか、どちらかの便り。 | |
| きはんせん | 機帆船 | 発動機と帆の両方を備えている小型の船。 | |
| ぎぼし | 擬宝珠 | ①橋の欄干の柱の上などにつける、丸くて先の尖った葱の花のような形の飾り。②葱の花。 | |
| きゅうせんぽう | 急先鋒 | 様々な活動の場で先頭に立ち、勢いよく進む人。 | |
| きゅうそだい | 窮措大 | 貧しい書生。貧乏な学者。 | |
| きょうそうきょく | 狂想曲 | 形式に拘らず自由な気分で作られた、快活で機知に富む楽曲。カプリッチオ。 | |
| きょうとうほ | 橋頭堡 | ①橋を守るため橋のたもとに築く陣地。②川や海から敵地に上陸するとき、そこを作戦・攻撃の拠点とする対岸の陣地。③勢力拡大のよりどころ。足場。 | |
| ぎょくあんか | 玉案下 | 手紙で脇付けとして宛名の左下に記し、相手に敬意を示す語。 | |
| きらぼし | 綺羅星 | ①きらきらと輝く沢山の美しい星。②優れた人が連なっているさま。 | |
| きりんじ | 麒麟児 | 将来が楽しみとされる、人並外れた優れた才能を持つ少年。 | |
| きんかんばん | 金看板 | ①金の文字で彫り込んだ看板。②世間に誇りを持って示す主義・技術・商品など。 | |
| きんじとう | 金字塔 | ①ピラミッド。②後世に残るような優れた業績や記録。 | |
| きんまんか | 金満家 | 大金持ち。財産家。資産家。 | |
| くうかんち | 空閑地 | 利用されていない土地。空き地。 | |
| くえにち | 凶会日 | 陰陽道ですべてに凶であるとする日。 | |
| くちはっちょう | 口八丁 | 喋ることが達者なこと。口上手。 | |
| ぐれんたい | 愚連隊 | 盛り場などをうろつき、ゆすりやたかりなどをする不良の集まり。 | |
| くろはえ | 黒南風 | 梅雨の初めころに吹く南風。 | |
| けいじか | 形而下 | ①形のあるもの。物質的なもの。②哲学で、時間や空間のうちに形を備えて現れるもの。その存在を感覚的に知ることのできるもの。 | |
| けいじじょう | 形而上 | ①形のないもの。抽象的な観念的なもの。②哲学で、時間・空間を超越して、感覚では存在を知り得ないもの。 | |
| げじきにち | 下食日 | 陰陽道で、天狗星が下界に下って食を求めるという日。この日は悪日として、沐浴、剃髪、種まきなどを忌んだ。 | |
| げっけいかん | 月桂冠 | ①月桂樹の枝葉を輪にした冠。古代ギリシャに置いて競技の勝者に与えられた。②栄光。勝利の象徴。最高に名誉ある地位。 | |
| けれんみ | 外連味 | 受狙いのはったりやごまかし。 | |
| けんぶじん | 賢夫人 | しっかりした賢い妻。賢明な婦人。 | |
| こういっつい | 好一対 | よく調和し、に遭っている組み合わせ。 | |
| こううんき | 耕耘機/耕運機 | 農作物の栽培を目的として、田畑を耕すための農業機械。 | |
| こうかくか | 好角家 | 相撲を見ることが好きな人。相撲好き。 | |
| ごうがしゃ | 恒河沙 | 非常に数が多いことのたとえ。 | |
| こうかぶつ | 好下物 | 良い酒の肴。佳肴。 | |
| こうこうや | 好々爺 | 人が良く善良な心を持つおじいさん。 | |
| こうこつかん | 硬骨漢 | 正義感が強く、強い意志を持ち、権力や筋力に簡単に屈しない男。骨のある男。 | |
| こうしんづか | 庚申塚 | 青面金剛を祀った塚。多く、道端の石塚。 | |
| こうずか | 好事家 | ①変わったものに興味を持つ人。②風流を好む人。 | |
| こうやがみ | 紙屋紙 | 平安時代、紙屋院で作られた上質の紙。のちには不要になった反故紙をすきかえしたうすずみ紙をいうようになった。 | |
| こうわきん | 汞和金 | 水銀と他の金属との合金。歯科治療などに用いる。アマルガム。 | |
| ごくさいしき | 極彩色 | 鮮やかな色を何色も使ったもの。また、けばけばしい色どり。 | |
| こけし | 子芥子 | ろくろで挽いた円筒状の胴に、丸い頭をつけて女児の顔を描き、胴に赤・青・黄などで彩色した木製の人形。 | |
| ごしょうらく | 後生楽 | ①死後の世界は安楽であると思い安心すること。②何事も苦にせず呑気なこと。 | |
| こそめづき | 木染月 | 陰暦8月の異称。 | |
| ごたくせん | 御託宣 | ①神仏のお告げ。②偉そうにくどくどと、勝手なことやつまらないことをいうこと。ごたく。 | |
| こっくり | 狐狗狸 | 占いの一種。三本の竹を交差させて組み、その上に盆を乗せて手で軽く押さえ、一人が祈り事をして盆の動きを見て占う。こっくりさん。 | |
| ごとべい | 五斗米 | 五斗(現在の五升)の米。転じて、わずかな俸禄のたとえ。 | |
| こぶくしゃ | 子福者 | 子宝に恵まれている人。子供をたくさん持ち、幸せな人。 | |
| こぼんのう | 子煩悩 | 自分の子を非常に可愛がり大切にすること。また、その人。 | |
| こむそう | 虚無僧 | 普家(ふけ)宗の托鉢僧。 | |
| ごめんそう | 御面相 | 顔つき。顔立ち。 | |
| こよぎ | 子負着 | 子供をおぶった上から着る着物。ねんねこ。 | |
| こわだんぱん | 強談判 | 自分の主張を通そうと強硬な態度で掛け合うこと。 | |
| コンガラ | 矜羯羅/金伽羅 | 不動明王の脇士の八大童子の第七。制多迦(せいたか)童子と対。 | |
| こんりんざい | 金輪際 | ①仏教において大地の一番底。②二度と。絶対に。 | |
| さいぎょうしん | 歳刑神 | 陰陽家のまつる地の守護神。毎年の干支をもとにしてその方角を決め、これに当たる土地の耕作を忌むという。 | |
| さいけいこく | 最恵国 | その国と通商条約や航海条約を結ぶ国々の中で、最も有利な取り扱いを受ける国。 | |
| さいげじき | 歳下食 | 歴注の一つ。天狗星の精が、人間の食を求めて下界に下るという凶の日。 | |
| さいじき | 歳時記 | ①1年の自然現象や行事などを解説した本。②俳諧歳時記の略。 | |
| さいづちあたま | 才槌頭 | 額と後頭部が突き出た頭。 | |
| さいばら | 催馬楽 | 古代の民謡を、平安時代に雅楽に取り入れてできた歌謡。 | |
| さぎちょう | 左義長/三毬杖 | 小正月中心に宮中で行われる厄除けの火祭り。民間では、門松や注連飾り、書初めなどを集めて焼く。どんど焼。どんど。 | |
| さくげんち | 策源地 | 戦地で、前線の部隊に必要な物資を供給する後方の基地。 | |
| さぐじ | 三狐神 | 農家でまつる田の神。みけつかみ。 | |
| さくぼうげつ | 朔望月 | 月が朔(新月)から次の朔、または望(満月)から次の望に至る周期の平均時間。太陰月。 | |
| さしものし | 指物師 | 木の板を組み合わせて箪笥や箱などを作る職人。 | |
| さっかしょう | 擦過傷 | すりきず。かすりきず。 | |
| さむえ | 作務衣 | 僧などが日常の作業をするときに着る衣服。 | |
| ざんかんじょう | 斬奸状 | 悪人を切るにあたって、その趣意を記した文書。 | |
| さんしちにち | 三七日 | 21日の間。21日間。特に、人の死後21日。 | |
| さんばいず | 三杯酢 | 酢と醤油とみりんまたは砂糖を適量に合わせた調味料。 | |
| さんばそう | 三番叟 | ①能の「翁」で、三番目に舞う老人の舞。②歌舞伎・人形浄瑠璃の幕開けに踊る祝儀の舞。 | |
| さんぷくつい | 三幅対 | ①3つで一揃いとなる掛物。②3つで1組となるもの。 | |
| ざんぼうりつ | 讒謗律 | 1875(明治8)年制定された言論規制法令。著作類によって人をあしざまに言う者を罰するという名目で、同日交付の新聞紙条例とともに政府批判に弾圧を加えたもの。 | |
| さんまくどう | 三悪道 | 悪業を行った者が死後にその報いを受ける、3つの苦しい世界。 | |
| さんりんぼう | 三隣亡 | 陰陽道の九星の一つ。この日に建築を始めると火事などの禍いがおこって、隣近所3軒をほろぼすという迷信がある。 | |
| しおりど | 枝折戸 | 木や竹の枝を並べただけの簡素な戸。多く庭の出入り口などに設ける。紫折戸とも。 | |
| じかせん | 耳下腺 | 両方の耳の下部の唾液腺。 | |
| しかんちゃ | 芝翫茶 | 染色の一つ。赤みを帯びた茶色。 | |
| しきさんば | 式三番 | ①能楽の「翁」の別称で祭儀的な演目。②歌舞伎で①を舞踊化したもの。 | |
| しきせ | 四季施 | ①主人が使用人に、その季節に応じた衣服を与えること。また、その衣服。盆と暮れの二度が普通。②江戸時代、幕府が諸役人に時服を与えること。 | |
| しきんせき | 試金石 | ①貴金属をこすりつけてその純度を調べるのに使う硬い石。黒色石英など。②人の才能や物の価値を試す物事。 | |
| しくんし | 四君子 | 中国画・日本画の画題で、ラン・キク・ウメ・タケのこと。いずれも気品があるので、四人の君主に例える。 | |
| しげめゆい | 滋目結 | 目結(四角形の図案)の柄を一面に染め出し、総絞りとしたもの。鹿の子絞りの総絞り。繁目結とも書く。 | |
| しころやね | 鐚屋根 | 母屋の屋根から一段低く差し出された屋根。 | |
| じざいかぎ | 自在鉤 | 囲炉裏や竈などの上に吊るした棒に取り付けて、掛けた鍋や鉄瓶の高さを自由に調整する仕組みのかぎ。 | |
| ししく | 獅子吼 | ①熱弁をふるうこと。大演説。「ーで人々は興奮の極に達した」②悪魔や外道をも恐れ伏せさせたという、獅子が吠えるよう¥な釈迦の説法。 | |
| ししんでん | 紫宸殿 | 平安京大内裏の正殿。新年の朝賀・即位・節会などの儀式が行われた。 | |
| じだらく | 自堕落 | 身を持ち崩して、だらしのないさま。ふしだら。 | |
| しちしちにち | 七七日 | 人の死後、(死亡の日を含めて)四十九日の日。また、その日に行う行事。 | |
| しっかいや | 悉皆屋 | ①江戸時代、大坂で注文を取り、京都に送って衣服の染色や染め直しをすることを職業とした人。②染物や洗い張りをする店。 | |
| シッタルタ | 悉達多 | 釈迦が出家前、太子だった時の名。 | |
| しゃこうしん | 射幸心/射倖心 | 偶然の利益や幸運をあてにする心。まぐれあたりを狙う心。 | |
| しゃばけ | 娑婆気 | 現世の名誉や利益に執着する心。俗念。しゃばっけ。 | |
| しゃもじ | 杓文字 | 飯や汁を掬う道具。特に、飯を盛る道具。 | |
| しゃりべつ | 舎利別 | 砂糖水を煮詰めた濃い液。シロップ。 | |
| しょうこんくつ | 消魂窟 | いろまち。遊里。 | コトバンク |
| しょうまきょう | 照魔鏡 | 悪魔を映し出す鏡。転じて、人間や社会の隠れた本当の姿をうつしだすもの。 | |
| じろうしゅ | 治聾酒 | 春の社日(春分・秋分に最も近い戊(つちのえ)の日)に飲む酒。 | |
| しろくぶん | 四六文 | 四六駢儷文の略。 | |
| ずいきまつり | 芋茎祭/瑞饋祭 | 京都の北野天満宮で10/1~4に行われる神事。芋茎で屋根を葺き、野菜・米・麦などで飾った神輿を担いで回る。 | |
| せがき | 施餓鬼 | 餓鬼道に落ちて飢餓に苦しむ亡者や無縁の亡者のために行う供養。 | |
| せむい | 施無畏 | ①仏・菩薩が衆生の恐れを取り除き、安心させること。②観世音菩薩の異称。 | |
| そくせんしょう | 塞栓症 | 血管をふさぐ不溶物により、血流障害を起こす病気。 | |
| たかびしゃ | 高飛車 | 相手の発言に耳を貸さず、自分の意見を一方的に押し付けるさま。 | |
| たかようじ | 高楊枝 | 食後にゆっくりと長い楊枝を使うこと。満腹したさま。 | |
| ちょうずばち | 手水鉢 | 手を洗う水を入れておく鉢。茶室の庭の飾りにも用いる。 | |
| つくもどころ | 作物所 | 平安時代、宮中の調度品の製造や修理を司った所。 | |
| てこまい | 手古舞 | 江戸時代、祭りに芸妓などが男装して鉄棒を突き、神輿や山車を前に歩きながら舞った舞。また、その舞い手。 | |
| てなずち | 手摩乳/手名椎 | 記紀神話に登場する神。出雲の国つ神であった脚摩乳(あしなずち)の妻で、奇稲田姫(くしなだひめ)の母。 | |
| ときひじ | 斎非時 | 僧侶の食事。また、法事などで僧侶に供する食事。 | |
| どくせんじょう | 独擅場 | ひとりだけが思うままに活躍するところ。独り舞台。 | |
| どくだんじょう | 独壇場 | 「独擅場(どくせんじょう)」に同じ。「擅」と「壇」とを間違えて慣用になった語。 | |
| としとくじん | 歳徳神 | 陰陽道で、その年の福徳を司る神。この神のいる方角を恵方といい、万事に吉とする。 | |
| とちめんぼう | 栃麺棒 | ①栃の実を原料とした食品の栃麺を延ばす棒。②うろたえ慌てること。また、慌て者。 | |
| どんかつかん | 鈍瞎漢 | にぶくて道理のわからない男。頭がわるくて理解力のない者。 | コトバンク |
| とんじんち | 貪瞋痴 | 貪欲(とんよく)、瞋恚(しんい)、愚痴の3つの根本的な煩悩。三毒。 | |
| とんちき | 頓痴気 | 気が利かない人。間抜け。 | |
| ながらび | 菜殻火 | アブラナを刈り干して種を取り去った、菜種柄を焚く火。特に、筑紫平野のものが有名。 | |
| にわかなりきん | 俄成金 | 急に金持ちになること。また、その人。 | |
| のんべえ | 飲兵衛 | 酒を飲むのが好きな人。大酒を飲む人。 | |
| はいかぐら | 灰神楽 | 火の気がある灰の中に湯や水などをこぼしたとき、勢いよく舞い上がる灰煙。 | |
| はなでんしゃ | 花電車 | 祝賀、記念などの行事の単に花や豆電球などで飾って走らせた市街電車。 | |
| びたいちもん | 鐚一文 | 極めて少ないお金のたとえ。 | |
| ひたきや | 火焼屋/火焚屋 | 平安時代、宮中で庭火や篝火をたいて夜の番をしていた小屋。 | |
| ひとよぎり | 一節切 | 昔の管楽器で尺八の一種。 | |
| ひのきぶたい | 檜舞台 | ①檜の薄い板を張った能楽・歌舞伎の舞台。②自分の腕前を広く世間に見せる晴れの場所。 | |
| ひろこうじ | 広小路 | 幅の広い街路。 | |
| ぼくねんじん | 朴念仁 | ①口数が少なく不愛想な人。②人情や道理の分からない人。わからずや。 | |
| みくだりはん | 三行半 | 江戸時代、夫が妻に与えた離縁状。転じて、離縁すること。 | |
| みみとしま | 耳年増 | 経験はあまりないが、聞きかじった知識は豊富にある若い女性。多く、性的な知識について用いる。 | |
| むすびのかみ | 産霊神 | ①自然界におけるすべてのものを生み出す神。②縁結びの神。 | |
| めであいづき | 愛逢月 | 陰暦7月の異称。 | |
| もぎどう | 没義道 | 人の道に外れていること。むごいこと。また、そのさま。非道。不人情。「ーに離縁した」 | |
| やこぜん | 野狐禅 | 禅修行で、まだ悟りきっていないのに悟ったと思い込んでうぬぼれること。また、そのような人。 | |
| やざま | 矢狭間 | 城壁などにあけた、矢を射るための小窓。 | |
| やぼてん | 野暮天 | 非常に野暮なこと。また、その人。「あいつはーだ」 | |
| ゆいまぎょう | 維摩経 | 大乗経典の一つ。古代インドの長者、維摩が在家のまま大乗の立場や根本的精神を戯曲的手法で説いたもの。 | |
| ゆうやろう | 遊冶郎/游冶郎 | 酒と女色に遊び耽る男。放蕩者。 | |
| よこれんぼ | 横恋慕 | 配偶者や恋人がいる人に、横合いから恋をすること。 | |
| よせんかい | 予餞会 | 卒業や旅立ちなどの前に行う、はなむけの送別会。 | |
| よたろう | 与太郎 | 知恵の足りない人。まぬけ。愚か者。 | |
| よもやま | 四方山 | 様々な方面。あちらこちら。転じて世間。 | |
| らくいんきょ | 楽隠居 | 子に跡目を譲り、隠居して安楽に生活すること。また、その人。 | |
| らくてんか | 楽天家 | 何事も良い方に明るく考える人。オプティミスト。 | |
| らんとうば | 卵塔場 | 台座の上に卵形の塔身を置いた墓石。 ②墓場のこと。 | 漢検漢字辞典の見出しは「らんとう」 |
参考資料
本ページは以下の書物を参考にしました。
1.漢検 漢字辞典
リンク
2.難読漢字辞典/三省堂
リンク
3.何でも読める難読漢字辞典/三省堂
リンク