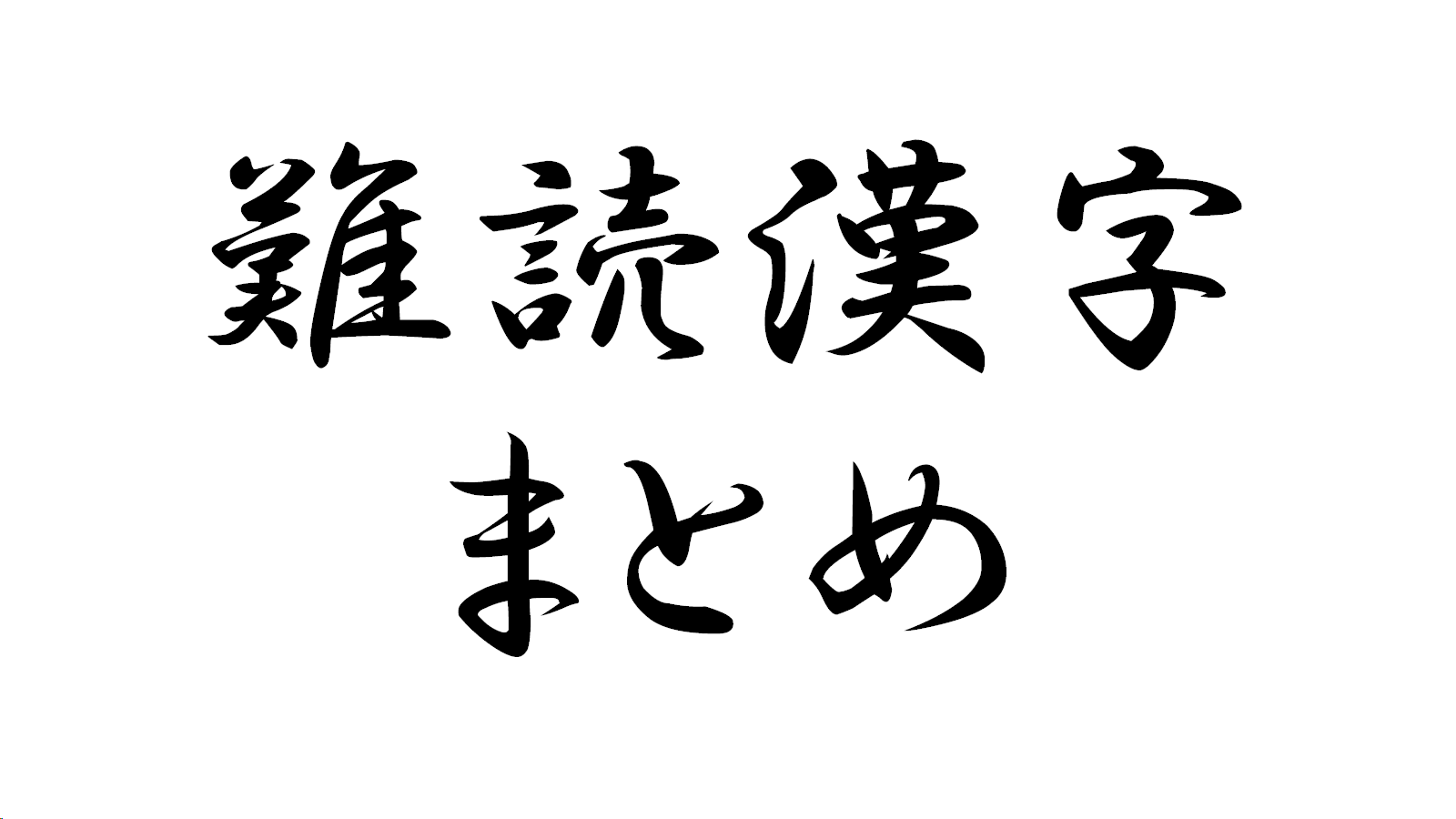外国地名を表す漢字をまとめてみました。
アメリカやイギリスを「米国」「英国」というように、現在でも日常的に使われているものもあれば、一方で殆ど使われなくなった表現も存在します。
なお、外国地名はその表記方法は様々存在し、諸説あるものもありますので、今回は「漢検漢字辞典」に見出し語として掲載されているもののみを列記します。
外国地名の名称一覧
| 国名 | 漢字 | 地域 | 種別 | 属する国名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド | 氷州 | 欧州 | 国 | ||
| アイルランド | 愛蘭 | 欧州 | 国 | ||
| アジア | 亜細亜 | アジア | 大陸 | ||
| アテネ | 雅典 | 欧州 | 都市 | ギリシャ | 首都 |
| アフリカ | 亜弗利加/阿弗利加 | アフリカ | 大陸 | ||
| アムール | 黒竜江 | アジア | 地域 | モンゴル、中国、ロシア | 河川 |
| アメリカ | 亜米利加/亜墨利加 | 北米 | 国 | ||
| アラビア | 亜剌比亜/亜拉毘亜 | 中東 | 地域 | サウジアラビア等 | 半島 |
| アルゼンチン | 亜爾然丁 | 中南米 | 国 | ||
| イギリス | 英吉利 | 欧州 | 国 | ||
| イスラエル | 以色列 | 中東 | 国 | ||
| イタリア | 伊太利 | 欧州 | 国 | ||
| イングランド | 英倫/英蘭土 | 欧州 | 国 | イギリス | |
| インド | 印度 | アジア | 国 | ||
| ウイーン | 維納 | 欧州 | 都市 | オーストリア | 首都 |
| ウラジオストク | 浦塩斯徳 | 欧州 | 都市 | ロシア | |
| ウルップとう | 得撫島 | 欧州・アジア | 地域 | 帰属未定 | |
| ウルムチ | 烏魯木斉 | アジア | 都市 | 中国 | 新疆ウイグル自治区の区都 |
| エジプト | 埃及 | アフリカ | 国 | ||
| オーストラリア | 濠太剌利 | 大洋州 | 国 | ||
| オックスフォード | 牛津 | 欧州 | 都市 | イギリス | |
| オランダ | 阿蘭陀/和蘭/和蘭陀 | 欧州 | 国 | ||
| カナダ | 加奈陀 | 北米 | 国 | ||
| カラコルム | 和林/和寧 | アジア | 都市 | モンゴル | 旧モンゴル帝国の首都 |
| カリフォルニア | 加州 | 北米 | 都市 | アメリカ | 州 |
| カンボジア | 柬蒲塞 | アジア | 国 | ||
| キューバ | 玖馬 | 中南米 | 国 | ||
| ギリシャ | 希臘 | 欧州 | 国 | ||
| ケンブリッジ | 剣橋 | 欧州 | 都市 | イギリス | |
| ゴア | 臥亜 | アジア | 地域 | インド | |
| コーカサス | 高加索 | 欧州 | 地域 | ロシア、アゼルバイジャン等 | 山脈 |
| ゴビ | 戈壁 | アジア | 地域 | 中国、モンゴル | 砂漠 |
| コロンビア | 哥倫比亜 | 中南米 | 国 | ||
| サクラメント | 桜府 | 北米 | 都市 | アメリカ | カリフォルニア州都 |
| サンフランシスコ | 桑港 | 北米 | 都市 | アメリカ | カリフォルニア州の都市 |
| シカゴ | 市俄古 | 北米 | 都市 | アメリカ | イリノイ州の都市 |
| シベリア | 西比利亜 | 欧州・アジア | 地域 | ロシア等 | |
| ジャワ | 爪哇 | アジア | 地域 | インドネシア | 島 |
| ジュネーブ | 寿府 | 欧州 | 都市 | スイス | |
| シンガポール | 新嘉坡 | アジア | 国・都市 | 共和国名、首都名どちらでも使用 | |
| シンガポール | 星港 | アジア | 都市 | シンガポール(共和国) | 首都 |
| スイス | 瑞西 | 欧州 | 国 | ||
| スウェーデン | 瑞典 | 欧州 | 国 | ||
| スエズ | 蘇士 | アフリカ | 都市 | エジプト | 運河 |
| スコットランド | 蘇格蘭 | 欧州 | 国 | イギリス | |
| スペイン | 西班牙 | 欧州 | 国 | ||
| セイロン | 錫蘭 | アジア | 地域 | スリランカ | 島 |
| タイ | 泰 | アジア | 国 | ||
| チチハル | 斉斉哈爾 | アジア | 都市 | 中国 | 黒竜江省の都市 |
| チベット | 西蔵 | アジア | 地域 | 中国 | 自治区 |
| チリ | 智利 | 中南米 | 国 | ||
| デンマーク | 丁抹 | 欧州 | 国 | ||
| ドイツ | 独逸 | 欧州 | 国 | ||
| トルコ | 土耳古 | 中東 | 国 | ||
| トルファン | 吐魯番 | アジア | 都市 | 中国 | 新疆ウイグル自治区の都市 |
| ニュージーランド | 新西蘭 | 大洋州 | 国 | ||
| ニューヨーク | 紐育 | 北米 | 都市 | アメリカ | 州 |
| ノルウェー | 諾威 | 欧州 | 国 | ||
| ハーグ | 海牙 | 欧州 | 都市 | オランダ | オランダ第3都市 |
| ハイチ | 海地 | 中南米 | 国 | ||
| パナマ | 巴奈馬 | 中南米 | 国 | ||
| ハノイ | 河内 | アジア | 都市 | ベトナム | 首都 |
| パリ | 巴里 | 欧州 | 都市 | フランス | 首都 |
| ハリウッド | 聖林 | 北米 | 地域 | アメリカ | カリフォルニア州ロサンゼルス市の地区 |
| バルカン | 巴爾幹 | 欧州 | 地域 | アルバニア、ボスニアヘルツェゴビナ等 | 東南ヨーロッパ、半島 |
| ハルビン | 哈爾賓/哈爾浜 | アジア | 都市 | 中国 | 黒竜江省の都市 |
| ハワイ | 布哇 | 北米 | 都市 | アメリカ | 州 |
| ハンガリー | 匈牙利/洪牙利 | 欧州 | 国 | ||
| ハンブルク | 海堡 | 欧州 | 都市 | ドイツ | |
| フィラデルフィア | 費府 | 北米 | 都市 | アメリカ | ペンシルバニア州の都市 |
| フィリピン | 比律賓 | アジア | 国 | ||
| フィンランド | 芬蘭 | 欧州 | 国 | ||
| ブラジル | 伯剌西爾 | 中南米 | 国 | ||
| フランス | 仏蘭西 | 欧州 | 国 | ||
| ブルガリア | 勃牙利 | 欧州 | 国 | ||
| ベトナム | 越南 | アジア | 国 | ||
| ベニス | 威内斯 | 欧州 | 都市 | イタリア | ベネチアの英名 |
| ペルー | 秘露 | 中南米 | 国 | ||
| ベルギー | 白耳義 | 欧州 | 国 | ||
| ベルリン | 伯林 | 欧州 | 都市 | ドイツ | 首都 |
| ポーランド | 波蘭 | 欧州 | 国 | ||
| ホノルル | 花瑠瑠 | 北米 | 都市 | アメリカ | ハワイ州都 |
| ポルトガル | 葡萄牙 | 欧州 | 国 | ||
| ホンコン | 香港 | アジア | 地域 | 中国 | 特別行政区 |
| マカオ | 澳門 | アジア | 地域 | 中国 | 特別行政区 |
| マレー | 馬来 | アジア | 地域 | マレーシア | 半島 |
| ミラノ | 未蘭 | 欧州 | 都市 | イタリア | |
| メキシコ | 墨西哥 | 中南米 | 国 | ||
| モスクワ | 莫斯科 | 欧州 | 都市 | ロシア | 首都 |
| モナコ | 摩納哥 | 欧州 | 国 | ||
| モロッコ | 摩洛哥 | アフリカ | 国 | ||
| モントリオール | 門土里留 | 北米 | 都市 | カナダ | ケベック州の都市 |
| ユダヤ | 猶太 | 中東 | 地域 | イスラエル | パレスチナ南部、ユダヤ教 |
| ヨーロッパ | 欧羅巴 | 欧州 | 大陸 | ||
| ラサ | 拉薩 | アジア | 地域 | 中国 | チベット自治区の区都 |
| リスボン | 里斯本 | 欧州 | 都市 | ポルトガル | 首都 |
| ルーマニア | 羅馬尼亜 | 欧州 | 国 | ||
| ルソン | 呂宋 | アジア | 地域 | フィリピン | 島(フィリピン最大) |
| ローマ | 羅馬 | 欧州 | 都市 | イタリア | 首都 |
| ロサンゼルス | 羅府 | 北米 | 都市 | アメリカ | カリフォルニア州の都市 |
| ロシア | 露西亜 | 欧州 | 国 | ||
| ロンドン | 倫敦 | 欧州 | 都市 | イギリス | 首都 |
| ワシントン | 華盛頓/華府 | 北米 | 都市 | アメリカ | 首都(コロンビア特別区) |
地域、種別については、2023年1月現在で外務省のホームページに公開されている「国・地域」を参照しています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html
なお、「漢検漢字辞典」に掲載されているものの、外国地名として列挙するのが微妙なもの、別立てで紹介する方が良いと思うものは以下にまとめました。
旧国名・旧称を表すもの
現存しない古代王朝や国家、現存するが呼び方が変わっている国など。
①ガンダーラ:健駄羅/乾陀羅
古代インドの地名。現在のパキスタン北西部ペシャワール付近。
②サイゴン:西貢/柴棍
旧ベトナム共和国(南ベトナム)の首都。現在のホーチミン市。
③シャム:暹羅
タイ王国の旧称。現代ではタイ原産の「シャム猫」としてその呼び方が残っています。
④ビルマ:緬甸
1989年にミャンマー連邦へ改名されるまでの同国の名称。ビルマの首都「ラングーン」も「ヤンゴン」に改称されました。現代では国名をカタカナ表記することが一般的であるためか「ミャンマー」を表す漢字表記は通俗的なものがなく、もし同国を漢字で表現したい場合は「緬甸」とせざるを得ません。
⑤プロシア:普魯西
プロイセンの英語名。もとドイツ連邦の中心的王国。第二次世界大戦後に東ドイツ、ポーランド、ソ連(現ロシア連邦)に分割。世界史では「普仏(ふふつ)戦争」などのように使われるため、「プロイセン=普」と当てることは比較的有名かも知れません。
⑥ヘブライ:希伯来
他民族がイスラエル民族やその文化、言語をいうときに用いた名称。ヘブル。また、パレスチナにあった古代王国の名称。イスラエルで使用されている言語は「ヘブライ語」ですね。
⑦ペルシャ:波斯
イランの旧称。「ペルシア」とも。「ペルシャ人」「ペルシャ語」をはじめ、湾岸戦争が発生した「ペルシャ湾」や「ペルシャ猫」「ペルシャ絨毯」など、イランやその周辺地域を表す言葉として今も多く使われています。
⑧ボンベイ:孟買
ムンバイ(=インドの都市)の旧称。「孟買」は「ムンバイ」の和名とされているため、必ずしも旧称のみを指す訳ではありませんが、漢検漢字辞典で旧称となっていたためこちらで紹介しています。
⑨ラオ:羅宇
現在のラオスで、インドシナ半島にある国のことです。また、ラオス産の竹で作った、キセルの雁首とその吸い口とをつなぐ管のことを「ラオ」と言い、その時にこの字を用います。
⑩ラングーン:蘭貢
④で紹介したとおり、ミャンマーの都市「ヤンゴン」の旧名です。
ちなみに「ビルマ」の首都は「ラングーン」でしたが、改称された後の「ミャンマー」の首都は「ヤンゴン」から「ネーピドー」に移っています(2006年)。したがって2023年1月現在、「ヤンゴン」は首都ではありません。
民族や言語を表すもの
特定の国や地域を指さず、民族や言語などの流動的なものの呼称。
①ウイグル:回鶻
中国の唐から元・宋にかけての時代にモンゴル高原などで活躍したトルコ系の民族。その後内乱などで四散し、現在は新疆ウイグル自治区の主要な構成民族となっています。
②ツングース:通古斯
東シベリアや中国東北部に住み、ツングース語を話す民族の総称。大部分は遊牧生活を営む。歴史で学ぶ「靺鞨(まっかつ)」はツングース系の民族ですね。
③ラテン:拉丁/羅甸
「ラテン語」「ラテン系」のように、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガルの人々のことを指します。中南米地域のことを「ラテンアメリカ」と称することがありますが、ラテン語を話すことからこのような言い方をするようです。
その他
更に例外的なものとしては、「メリケン:米利堅」があります。「メリケン」とは「アメリカン」が訛った表現で、意味合いとしてはアメリカそのものやアメリカ人を指します。
近年では使うことも稀ですが、「メリケン粉」とは「小麦粉」のことを指すほか、漢検漢字辞典では「メリケン波止場」というものも例示として載せており、これは神戸港にある波止場のことです。現在は「神戸港震災メモリアルパーク」という公園になっています。
更に、拳骨で殴られることを「―を食う」のように表現することがあり、このイメージでは「メリケンサック」という武器が連想されます。ちなみにメリケンサックは「ナックルダスター」とも呼ばれるそうですが、それは余談過ぎるかも知れません。